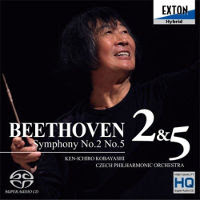キーシンによるラフマニノフのピアノ協奏曲第2番

エフゲニー・キーシンのピアノ、ワレリー・ゲルギエフ指揮ロンドン交響楽団。1988年のセッション録音。 キーシンが16歳の頃の録音。 個人的には、ラフマニノフのピアノ協奏曲の中では、第3番の存在感が圧倒的。2番の協奏曲には、これといった思い入れはなく、特別に愛聴する音源もない。 ただ、2番第一楽章の展開部はスリリングで、この曲を聴く動機の半分以上は、ここを聴くためだったりする。 :::::::::: キーシンのピアノは、巧くて、タッチが綺麗で、自然なスケール感を作り出している。緩急の幅のある表現だけど、音楽の展開に即していて、一切の無理を感じさせない。 レベルの高いピアノだけど、ハッとさせられるような技芸みたいなものは乏しいかも。 この音源の魅力は、キーシン個人のピアノより、ピアノとオーケストラが一体として作り上げる、バランスの良い作品像だろうか。 :::::::::: この演奏から、ゲルギエフが出しゃばっている印象を受けないけれど、キーシンのピアノが薄味な分、ゲルギエフのうまみが前に出ているように聴こえる。 どちらが主導しているのかは判断できないけれど、ゲルギエフが、この曲の俗っぽさを、品良く、恰幅よく聴かせて、キーシンのクリアで華やかなピアノが、 さらに彩度とか鮮度を高めている。 楽曲を楽しむという目的には、好適な音源だと思う。