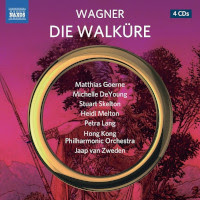MX Linuxを旧型ThinkPadに導入

現在、持ち運び用のノートパソコンは、ThinkPad T410sという、古いモデルを使っています。 2010年発売のモデルです。CPUはi5-540Mです。 これをあえて使っている理由は、いくつかありますが、14.1 インチで解像度1440x900のディプレイです。 ThinkPadのT4○○シリーズは、この次のT420から、14.0インチで解像度最大1600x900に改定されてしまいました。 ディスプレイのサイズが微妙に小さくなって。横長に。 表示性能は上がっているのでしょうけれど、作業効率とか眼の負担を考えると、14.1 インチで1440x900の方が、しっくりきます。 個人的には、もっと正方形に近づいてほしいですが、無いものねだりです。 ただ、旧式であることとは別に、T410sにははっきりとした欠点が複数あるので、人様にはお勧めできません。 :::::::::: このT410sをLinuxで動かしたかったのですが、予想外に難航しました。このたびようやくMX Linuxに落ち着きそうだという、わりとどうでもよい話題です。 最後まで引っかかったのは、次の3点でした。 xgammmaコマンドが効く。 ハードウェアの明るさ調整が効く。 ストレスのない処理速度。 初めに、Linux Mint Cinnamon19.2を試しました。Cinnamonは重いと聞いていましたが、SSDなので何とかなるかと。 標準でインストールしたところ、xgammaコマンドもハードウェアの明るさ調整も効きません。 ガンマと明るさを調節できるアプレットがあることを知り、これをインストールしました。これは動作しましたが効きが悪い。望むような表示になりません。 はたと気がついて、nVidiaのドライバーをインストール。T410sには古いGPUが組み込まれているので。 nVidiaドライバはインストールできて、自動的にnouveauを無効化してくれました。 それで、ハードウェアの明るさ調整は使用可能に。 ただ、xgammaコマンドの方は、相変わらず効きません。 それと、Linux Mint Cinnamonには、もう一つ困ったことが。 全体的に動作速度はスムーズでしたが、ブラウザでの文字入力のときに、...