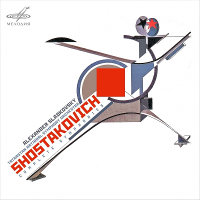オットー・クレンぺラー指揮フィルハーモニア管弦楽団。 1959年のセッション録音。交響曲全集から。 クレンペラーのテンポ感の崩壊が見え始めたのが1950年代の終盤からで、ベートーヴェンの交響曲全集は、ちょうどその移行期に録音された。 そのためにこの全集は、興味深くも奇妙な仕上がりになっている。そんな中で「英雄」は崩壊後の方で、かなり遅いテンポ。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-* もっとも、この演奏を聴いて「崩壊」という言葉を連想させられることはないだろう。数年間に起こったテンポ感の変化が、あまりに極端なので「崩壊」というくらい大げさな言葉を使いたくなるけれど、個々の演奏が崩壊しているわけではない。 むしろ、この「英雄」などは、滅多にないくらい堅固で明晰に仕上がっている。演奏として全く崩れていない。 むしろ、このテンポなのに、停滞感や粘着感が一切ないところに、この指揮者の非凡な特質が表れている。 録音当時すでに70代半ばだけど、彼の耳は健在だったようで(推測)、その統率力とあいまって、質のそろったクリアなサウンドに仕上がっている。 そして、特筆したいのがそのリズム感。クレンペラーに限らずワールドクラスの演奏家だったら、リズム感は良いに決まっているのだけど、クレンペラーはこのテンポで音楽全体を躍動させる。こういう感じは、他に記憶がない。 彼の演奏スタイルは、構造や書法から楽曲にアプローチする典型であるにもかかわらず、 その音楽に生命感の横溢を感じさせる源泉は、このリズム感にある。 このリズム感はたぶん生来のもので、狙ってやっているわけではないのだろうけど、テンポ崩壊後のクレンペラーの演奏様式では、遅い足取りと躍動するリズム感との取り合わせが、際立って特徴的。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-* クレンペラーにとって得意曲だったようで、EMIへの正規録音は2つだけだが、ライブ音源が多数あり、映像も残っている。 EMIに残されたもう一つの音源は、1955年のモノラル録音で、 これでも堂々として聴こえるが、今回取り上げる音源より4分も短い。 EMIの音源なら、1955年の方が好みというか、クレンペラーにとって屈指の音源ではないかと思っている。 楽曲へのアプローチは1959年録音と変わりない...