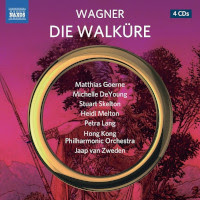ヤンソンスによるシューベルト交響曲第8(9)番「グレート」(2018年ライブ)

マリス・ヤンソンス指揮バイエルン放送交響楽団。 2018年2月1〜2日のライブ録音。 ヤンソンスは、1943年にラトビアで生まれ2019年に亡くなった指揮者。 2003年から亡くなるまで、このオーケストラの首席指揮者の地位にあった。 バイエルン放送交響楽団も、またヤンソンスが2004〜2015年にかけて常任指揮者を務めたロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団も、彼の在任中に自主レーベルを立ち上げた。 たまたまなのか、ヤンソンスが推進役だったのか知らないが、この音源はそんな中の一枚。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-* ヤンソンスは、その特徴を言葉にしにくい指揮者。 わたしが知る範囲のヤンソンスは、自分の個性をひけらかさず、もっばら楽曲とオーケストラの持ち味を引き出すことで耳を楽しませる指揮者。 個性が薄いということではないけれど、譲れない確たる美意識があって、共演者をその世界に引き込んでしまうというタイプではない。 こういうアプローチで、世界のトップに居続けられたというのは、基本的な能力がすこぶる高いのだろう。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-* ヤンソンスの平明な造形感が、楽曲の古典的に側面とマッチしていることもあって、模範的かつ爽快な仕上がりになっている。 足取りは軽快だけど、恰幅の良いサウンドバランスのせいで、腰の軽さは感じられない。 オーケストラの機能性と明るくて柔らかいサウンドが十分に引き出されて、本場っぽいテイストも随分と醸し出されている。厚みを感じさせるけれど、重厚さより豊かさが勝っている。 本場風を気取っている感じもオーケストラに譲る感じもなく、ともに演奏することを満喫しているような自然体。 亡くなる前年とは思えないくらい推進力とか力感があるけれど、むちろん強引さはない。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-* 完成度の高い魅力的な演奏だけど、好みを言わせてもらえば、この曲ではもっと締まりのある響きで、個々のパートを鮮度高く聴かせてほしい。 とくに木管パートの音色の色彩感をもっと楽しませてほしかった。そのあたりもこの曲の聴きどころと思っているので。