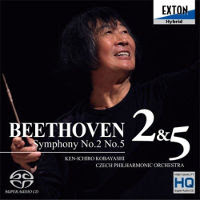ナガノのサン=サーンス交響曲第3番『オルガン付』

ケント・ナガノ指揮モントリオール交響楽団。 2014年のライブ録音。 ナガノは2006年から、同オーケストラの音楽監督を務めている。 前音楽監督デュトワは、1982年に、このオーケストラと同曲をセッション録音。 指揮者も体制も違うし、30年を超える隔たりもあるし、ナガノ盤に、デュトワ盤を偲ばせる要素はない。 :::::::::: 明解に、端正に、精緻に。これらを合言葉に、実直に作り上げられている。 弦を雄弁に歌わせて、表情にメリハリをつける、というタイプではない。すべてのパートが均等に近い目の細かさで編み上げられている。 全体的にお堅い演奏スタイルだけど、サービス精神だってある。第二部後半は壮麗に盛り上げて、特に終盤でのティンパニの瞬発力は痛快。他の音源と比べても、記憶に残るほど効果的。 :::::::::: ところで、ナガノの演奏スタイルは、すべてのパートをクリアに、均質に響かせることを志向しているようだけど、だとしたら、それ自体は不徹底に感じられる。 サウンドは緻密風だけど、実際には埋没しているフレーズとか、少なからずある。肌理は細かくても、精緻とまでは言えない。 生演奏ゆえに割り切ったところがあるのかもしれない。生なら「終わり良ければ総て良し」でも、こうして記録として鑑賞すると、割り切れないものが残る。